劇評家を待ちながら〜web版のための序文〜
私と演劇とは、長く「友人の友人」という程度の付き合いだった。つまり、友人との会話に登場するし会う機会もあるけれど、二人きりで会うことはあまりない、というぐらいの関係だ。
札幌で就職してすぐに、誘われて演劇鑑賞団体である「札幌えんかん」に入ったけれど1年で退会した。しばしば劇団四季の舞台を観に行ったけれど、それは友人が熱烈なファンだったからだ。タウン情報誌を看板に持つ出版社に転職し、飲み友達になった編集部の演劇担当からディープな話を聞かされもしたけれど、小劇場に通うようにはならなかった。劇団イナダ組が観客動員数1万人を達成した熱狂を聞き、チームナックスのメンバーによる小さな舞台を仕切る仕事にも携わったというのに、だ。
やがてフリーライターになり、縁あって、道外から講師を招いておこなわれた演出家・戯曲家養成講座の内容をまとめる仕事に3年続けて携わった。これはとてもエキサイティングな体験だった。時代の流れの中で戯曲というものが何を試みているのか、セリフの襞に隠されているものの存在、演出家はそれをどのように読み解いていくのか、などについての圧倒的な思考を浴びて、けれど、がぜん興味を持って観に行った北海道の演劇は、講師たちの語りほどには刺激的ではなかった。それでも、「仕事上でしばしば付き合いのある利害関係のない知人」くらいの関係が続くうちに、いくつかの魅力的な作品に出会いもし、何より北海道での演劇創造のためのフレームづくりを行う人たちの熱心さに心惹かれ、北海道の演劇文化がどのような状態にあるのか、どう変化していこうとしているのかについて関心を持つようになった。
季刊誌「カイ」19号のリニューアルでカルチャーコラム書くよう命じられたとき、私はジャンルとして「演劇」を選択した。これがきっかけとなり、演劇創造をサポートする立場の人たちから、札幌劇場祭の審査員などいくつかの「演劇を観る役割」を依頼され、務めをより誠実に果たすために、その他の演劇も恒常的に観るようになった。
観て発見したものについて書きたくなるのはライターの性だ。けれど、演劇について書こうとするとき、いつも気後れのような感情が付いてくる。
北海道で、演劇作品について語られる言葉は優しく温かいものばかりだ。目に見えるところでは。批判的な感想は演劇の作り手には聞こえないところで、大抵は言葉を濁しながら語られている。そのような空気の中で、大多数とは異なる個人的な考えを発信するのは、私にとっては少しばかり余分なエネルギーを必要とする行為だ。何より、「人が精魂込めて創り上げたものについて何かを言えるような立場なのか、お前は?」という声が、自分の内側からも聞こえてくる。
とはいえ実のところ、観劇後に「どう観たか」について観客同士で忌憚なく語ることが、私にとっては演劇鑑賞における最大の楽しみなのだ。思うところを好きなように語って何が悪いというのだろう。プロ野球やサッカーのファンは、負け試合の後にはビールを飲みながら選手のミスを罵り監督の采配をあげつらい、あの場面ではこうするべきだった!と熱く語り合ったりするではないか? プレイが良かれ悪しかれ、それをきっかけにコミュニケーションが生まれることがファンの楽しみではないか?
翻ってみれば、北海道の演劇、その中心的な存在である札幌の演劇の状況は、劇団数も上演数も多く活況に見えているものの、観客の楽しみ方は草野球に近いのではないだろうか。つまり、知り合いのプレイを見守り、同じ空間に立つ身近なヒーローやヒロインの活躍を楽しみ、温かく励ます、というスタイルだ。
演劇の作り手たちはどのように感じているのだろう。草野球のヒーローとして楽しくプレイすることが望みなのか。それとも、時には容赦のないブーイングを浴びることも覚悟の上で、身内ではない人たちにも自分たちのプレイを観てほしいと望んでいるのだろうか。
気後れと、思うがままに語り尽くしたい欲求との間で揺れ動きながら、私はこの「客席の迷想録-北海道ステージウオッチング」を書いている。
ここでは北海道で上演される演劇を中心としたステージを観て、客席でもやもやと浮かんできた考えを言葉にしている。書き手である私は演劇の専門家ではなく、ただの観客にすぎない。作品の、演劇史における立ち位置や挑戦にはほとんど無関心だし、世界はもちろん、現代の日本の演劇の中心である東京の演劇を観に行くこともほとんどしない。私が関心を持つのは、北海道で生きる人たちが作る舞台、北海道で生きる私たちに観せるためにここで上演される舞台だ。それ以外の演劇への関心はそれらをよりよく理解するためで、つまり、私の演劇への関心は北海道への関心の延長上にある。
なので、このコラムは正しい意味での劇評とは違うものだ。けれど、私が客席でのもやもやを書くことで、多くの観客が「あ、こんなふうに好き勝手な見方をしてもいいんだ」と感じて、作り手に気兼ねすることなくいろんな意見を発信するようになればいいな、と思う。観客同士、相容れない感想があっていい。そこが面白いのだから。客席の声が賑やかになり、ときにはその声が作り手側に届いて、苛立ったり喜んだりしたことが次の作品に繋がるスリリングな関係性が生まれたら、とても素敵だと思う。作られる作品は強度を増し、観客はより多様な視点を持つようになり、相互作用の中からやがて時代と世界に響く作品が生まれて、そうなれば広く世界の演劇の流れにおける北海道の演劇というものについて書く劇評家が現れるかもしれない。
私はその人が書いたものを通じて、新たな視点から北海道とそこで作られる演劇を発見するだろう。
そのような北海道の演劇作品と劇評家を待ちながら、私はこのコラムを書いているのだ。たぶん。
岩﨑真紀(いわさき・まき)
情報誌・広報誌の制作などに携わるフリーランスのライター・編集者。特に農業分野に強い。来道した劇作家・演出家への取材をきっかけに、北海道で上演される舞台に興味を持つ。TGR札幌劇場祭2014~2016年審査員、シアターZOO企画・提携公演【Re:Z】2015~2016年度幹事。サンピアザ劇場神谷演劇賞2017年度審査員。

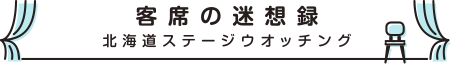 岩﨑真紀-text
岩﨑真紀-text

