
前浜に設けられた真昆布の養殖場。漁師は「昆布の畑」と呼ぶ(提供:鹿部温泉観光協会)

前浜に設けられた真昆布の養殖場。漁師は「昆布の畑」と呼ぶ(提供:鹿部温泉観光協会)
函館から車で約1時間。
鹿部といえば思い浮かぶのは、間歇泉、たらこ、ファイターズの伊藤大海投手…。
訪ねた道の駅しかべ間歇泉公園の入り口でも、伊藤大海投手の等身大パネルが出迎えてくれた。
人口は約3500人。海と山に挟まれているため農地が少なく、漁業と水産加工が基幹産業の「海のまち」である。
9年前、北海道新幹線の開業にあわせてオープンした道の駅では、漁協の女性部が運営する「浜のかあさん食堂」が人気を集めている。

道の駅しかべ間歇泉公園。漁協の女性部が運営する「浜のかあさん食堂」が大人気

「浜のかあさん食堂」ではその日水揚げされた魚でつくる御膳が評判。この日はアサバカレイの煮付け
その鹿部町でいま話題なのが、体験観光プログラム「こんぶのまちで学ぶブルーカーボンツアー」である。
北海道観光機構の伴走支援事業において令和6年度の優秀賞を受賞した。
企画したのは、鹿部温泉観光協会の金澤佑さん。その狙いをこう話す。
「コロナ禍で町内唯一の大型宿泊施設だったロイヤルホテルが閉館したんです。これはまちにとって大きな痛手。そこで教育旅行の体験プログラムに力を入れて、町外から人を呼びこみたいと考えました。その際にテーマに据えたのが昆布です。そもそも鹿部は昆布漁で発展したまちですので、まちのアイデンティティという意味で昆布を中心に組み立てました」

鹿部温泉観光協会の金澤佑さん。函館出身。箱根の観光ホテルで働いていたが、東日本大震災のボランティアをきっかけに、地域のための仕事がしたいとUターンした
道南で採れる真昆布のうち、鹿部から函館市南茅部地区までの限られたエリアで採れるものだけが「白口浜真昆布」と呼ばれている。
切り口が白く出汁をとったときに色が濁らないのが特徴。
江戸時代には真昆布の最高級品として松前藩が朝廷や将軍家に献上されていたという。
いまは日清食品のカップ麺「どん兵衛」のつゆにも使われているそうだ。
「なぜここでしか採れないのか。駒ヶ岳の大噴火の噴出物が海の中に堆積していて、昆布の栄養になるケイ素が豊富だからという話も聞きますが、はっきりとはわかっていません」
まちの基礎をつくった昆布について、もっと多くの人に知ってもらおうと、金澤さんはまちの人の協力を仰ぎ、さまざまなプログラムを考えた。
昆布漁の時期には昆布干し体験、漁のない時期には昆布の加工体験。
さらにアイデアを凝らして、漁師さんと一緒に磯舟に乗って養殖施設の見学、昆布の繁茂する海中林に設置したカゴを引き揚げて海中生物の調査、漁協の女性部による昆布を使った料理教室など、季節や天気に合わせて選択できる幅広いプログラムを用意している。
いずれもSDGsに沿った環境教育の視点を盛り込んでいるのが特徴で、料金も内容によるが1人3000円程度とリーズナブルに設定。修学旅行生をはじめ、ここ数年は海外からの参加者も増えつつあるという。
地元の人とふれあいながら鹿部でしかできない体験ができる。
旅行者は興味をそそられるが、受け入れる側の町民はどうなのか。
仕事を中断して旅行客の相手をするのは負担にならないのだろうか。
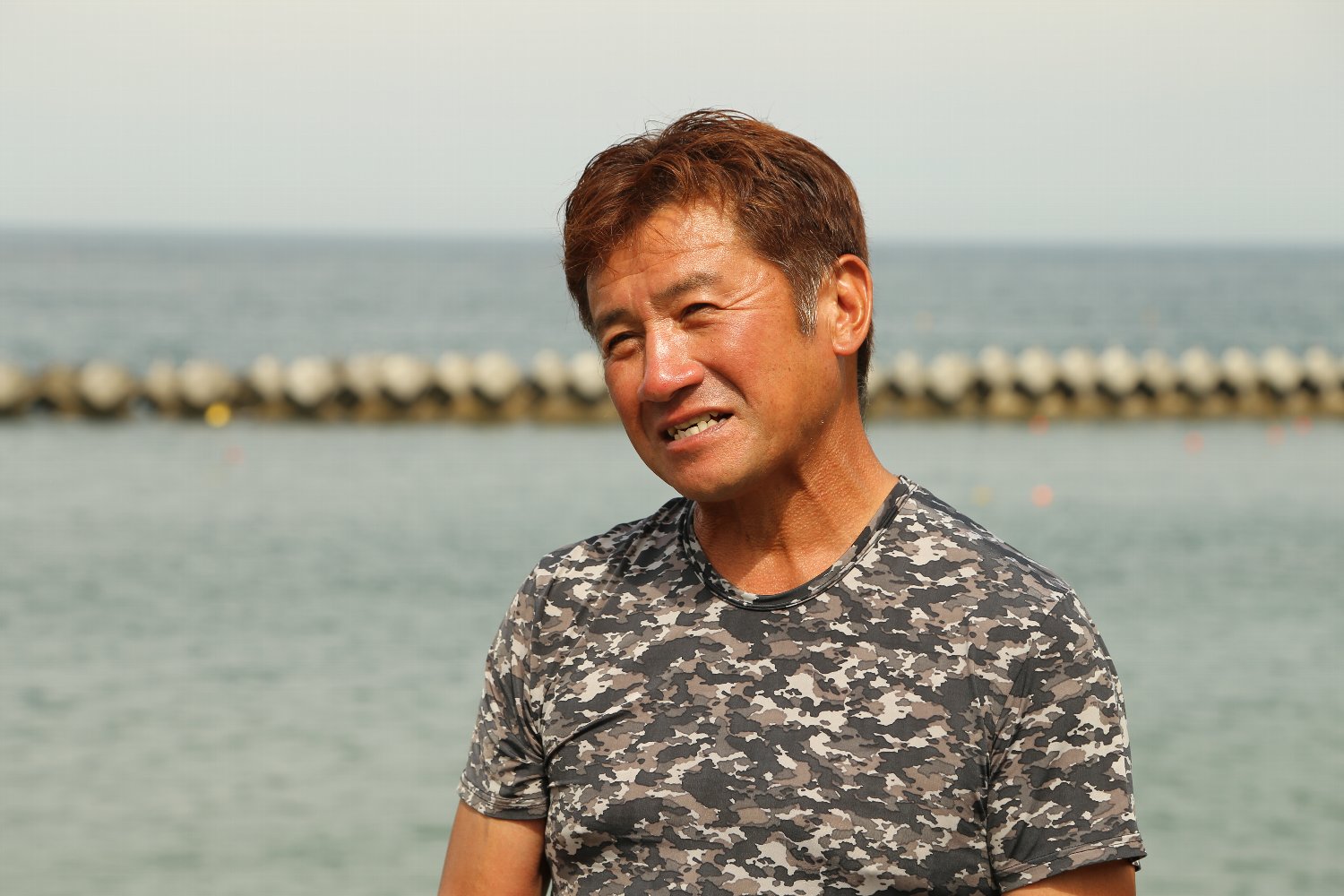
昆布漁師の飯田英和さん。真冬に養殖昆布の剪定作業を行うなど、こまめな手入れを実践。「ヒデ、ずいぶんいい昆布とるようになったな」と周囲に褒められたのが「泣きたいくらいうれしかった」と言う
答えてくれたのは、昆布漁師の飯田英和さん。
昆布漁最盛期の8月上旬、早朝3時から海に出ていたにもかかわらず、多忙な時間を割いて話を聞かせてくれた。
「せっかく来てくれるんだから、そこは切り替えてやってるね。人口も減って漁師もだんだん少なくなってきているし、このままだと先細りだから。鹿部のことも漁業の現場のことも、みんなにもっと知ってもらいたいからね」

水揚げした昆布はすぐに洗浄し、根を切り落として乾燥室へ

熱風で昆布を乾かす乾燥室。真昆布は幅が広く身が肉厚なのが特徴
飯田さんのところでは、7〜8月の昆布漁の時期は昆布干しの体験。
漁期以外は乾燥させて貯蔵してある昆布を加工する作業を体験してもらうという。
昆布をサウナみたいな機械に入れて、蒸気でいったん蒸し、やわらかくしてから、シワを伸ばして平らに加工する。昆布の耳といわれる端の部分をハサミで切って整えたり、部位別に裁断したりを体験しながら、飯田さんに昆布養殖や漁のことをくわしく教えてもらえるそうだ。
「最初は緊張して、言いたいことも言えねがったけど、だんだん会話もスムーズになってきたかな」と照れる飯田さん。独特のイントネーションがある浜言葉も耳に心地良い。
「栃木とか海がないところから新幹線でやってくる子は、昆布の大きさにびっくりして、えらい感動してくれる。こっちも新鮮な気持ちになるんだわ。漁師以外の人の話を聞くのは、自分にとってもプラスになるしね」
本州の高校生、スペイン・バスク地方のシェフ、さまざまな人が飯田さんの作業場を訪れて、飯田さんの昆布漁の話に耳を傾けてくれたという。

乾燥した昆布を積み重ねて熟成させる倉庫。昆布のいい香りが広がっている
元漁師の和田泰治さんも体験観光プログラムに協力を惜しまない町民の一人だ。
北海道立漁業研修所の講師をしていた経験を生かして、暮らしに役立つロープワークや海と森のつながりを参加者に伝えている。

元漁師の和田泰治さん。腰を痛めて漁師を辞めてからは、町内にある道立漁業研修所の実習船の船長に。漁業者の育成に努めてきた
「漁師にとってロープワークは死活問題。まっくらな中でロープを操ることができないと、命に関わります。絶対にほどけない、それでいて締まりすぎない、そしてほどこうと思えば簡単にほどける、そうした結び方を覚えておけば、万が一の災害時、自分や周りの人を助けられます」
修学旅行生に短時間で覚えられるロープワークを教えたり、ガラスの浮き玉を懐かしむ人には縄で編み包む昔ながらの技術を伝授したりすることもある。
「浮きの素材は昔は木でした。そのあとガラスに変わりましたが、ガラスはぶつかれば割れてしまう。でも縄でくくっておけば落としても割れません。今は浮きがプラスチック製になって、こうした技術も使われなくなりました」
漁の道具の変遷や漁師の哲学も織り交ぜながら、参加者に語りかける和田さん。
ハワイから来た親子は、レジャー用の船を持っていると言い、和田さんのロープワークを興味津々で学んでいったという。
言葉が通じなくても、手でやって見せれば理解できるし、真似することもできる。
インバウンドの旅行者にも喜ばれる理由は、そのあたりにあるのかもしれない。

漁の道具の変遷を説明しながら、ガラスの浮き玉を縄で編む技を教えてくれる
和田さんは所有する山に旅行客を案内し、海を守るための森づくりを体験してもらうプログラムも実践している。枝払いや下草刈りなどの森の手入れ、苗木の植樹など、参加者が体験できる内容は季節によって異なるが、森と海のつながりを体感してもらうことがねらいだ。
「漁師が森づくりというと、なんで? と思うかもしれないけど。オレのじいさんの夢は、自分で育てた木で船を新造して、それで魚を捕ること。オレは小学校に上がるくらいによく山に連れていかれて、この木は船のどこに使う木かを聞かされました。船の底の基礎になるのはラクヨウ(カラマツ)。油分があるから腐れにくい。船の外板は加工がしやすいスギ、内側はナラ、エンジンを乗せる部分はクリ。そういって手入れをしながら木を育てたんです」

和田さんの森で木の手入れや植樹を体験。森と海がつながっていることを学ぶ(提供:鹿部温泉観光協会)
木を大きく育てるには枝を払って風を通し、日当たりを良くしなければならないこと。
根がしっかりと広がれば、根元の土をつかまえて、多少の雨では土砂が流出しないこと。
枯れ葉が腐葉土をつくり、いつしか川を通じて海を育てる栄養になること。
難しいことは分からなくても、実際に森を歩いた子どもたちは、地面がふかふかだったことをきっと忘れないだろう。
町民との交流を主眼において、鹿部らしい体験を次々とプログラム化してきた金澤さん。参加者は年々増えていても、「目的は観光客の誘致ではない」と言う。
「目指しているのは地域の産業の活性化です。そこにつながる観光じゃないと意味がない。地域の人と交流して、このまちを好きになってもらい、ちゃんと収益にもつながる。そんなプログラムにしたいし、今後は社会の課題も学びの材料にして子どもたちと一緒に考えていけたらいいなと思っています」
励みにしているのは参加者から届くお礼のメールだ。
「鹿部の人はみんなあったかくて、すごくいい経験ができました」
「鹿部いいところですね」「また行きたいです」
昆布を見るたびに鹿部の海を思い出す、そんな人が全国に少しずつ増えていくとしたら、なんて素晴らしいことだろう。

近年、天然昆布の漁獲量が減少、資源維持のため漁協が漁を休止。今年は3年ぶりに天然昆布の漁が3日間だけ行われた(提供:鹿部温泉観光協会)
金澤さんによると、豊臣秀吉が大阪城を築く際、濡らした昆布を敷き、ぬめりを利用して石垣用の巨石を運んだという説があるという。
「鹿部町も駒ヶ岳の噴火で何度も廃村の危機を迎えましたが、そのたびに昆布漁を再開し、復興させた歴史があります」
昆布が果たしてきた役割は私たちが思うより、ずっと大きいのかもしれない。
さらに今、注目を浴びているのがブルーカーボンの可能性だ。
ブルーカーボンとは海草や海藻が海中に取り込み蓄積する炭素のこと。
なかでも昆布は大きな海藻なので、光合成の効率が高くCO2吸収源としての期待が大きい。
「カーボンクレジットによる収入に結びつくかもしれません。現在、投石などで藻場を再生する取り組みが行われていますが、浜を甦らせるのも長期スパンでの自分の仕事だと思っています」
体験観光のプログラムの企画から、コーディネート、当日のアテンドをほぼ一人でこなす金澤さん。広い視野と長い視点で、鹿部町の未来を見据えている。

約10分間隔で15mもの高さまで噴き上がる間歇泉。噴き上がった温泉は足湯として来園者を楽しませている(提供:鹿部温泉観光協会)