
操業中のれんが工場では道内最古、1939(昭和14)年に江別市元野幌で操業を開始した米澤煉瓦株式会社

操業中のれんが工場では道内最古、1939(昭和14)年に江別市元野幌で操業を開始した米澤煉瓦株式会社
江別では昭和30年代に10社以上のれんが工場が操業していたが、次第にその数が減り、現在は2社のみとなった。今回改修した赤れんが庁舎のれんが製造を一手に引き受けたのは、そのうちの1社、米澤煉瓦株式会社である。専務取締役の米澤秀則さんが、こう説明してくれた。
「従来の庁舎では四角いれんがを斜めに積んだり凸凹に並べたり、いろいろな積み方で壁の複雑な意匠をつくっていました。しかし今回の改修では耐震構造にするため、ある一つの面でれんがをスパッと一直線に揃えないといけない。そのためにサイズを微妙に変えたり、三角形にしたり、特殊な形状のれんがが必要になりました。何度も打ち合わせを重ね、結局全部で34種類、1万個強のれんがを納品しました」
特殊な形状のれんがはどうやって作るのだろう?
「例えば、こういう曲面のあるれんがの場合、まず大きな四角い型枠で抜き、職人がアールの型に沿って一つずつピアノ線で切っていきます。そのあと乾燥させて焼きますが、乾燥しやすいように穴を開ける加工も全部手作業で行います。焼き上がると縮むため、その分を正確に見越して成形し、その他の工程でも細かい調整が必要です。要は、すごく手間がかかって難しい。いまでは受注していない工場も多いと思います」

米澤煉瓦の専務取締役・米澤秀則さん。手に持っているのは屋根の下などに用いられる「鳩胸れんが」

2019年12月から続いた大規模改修を経て2025年7月25日にリニューアルオープンした赤れんが庁舎。屋根中央部・ドーム型の八角塔は一度取り外されるなど工事が大きな話題となった。その部分を含めて、新しく用いるれんがの全てを米澤煉瓦が納めた(撮影:伊田行孝)
他の工場では作れないため、様々な相談がもちこまれる。特殊な形だけでなく、れんがの色は原料の粘土や焼成温度など様々な条件によって決まるが、古い建物を改修する際は「これに近い色にしてください」と頼まれることが多い。その場合も米澤煉瓦では繊細な“色合わせ”をして、基本の5色(赤色・焼過色・中性色・還元色・マンガン色)以外にも柔軟に対応してくれる。
「オレンジに近い色ならこの成分を少し加えてみようとか、色の近似値をとるのがわりと得意なんです。うちの会社は先代の頃から、まちの『れんが屋さん』という雰囲気があって、それをずっと大切にしてきました。昔はSNSなどありませんが、良いれんがを作ればそれ自体が広告となって『米澤煉瓦は質が良い』と口コミで広がります。なので、先代はとにかく良いものを作ることに力を尽くしました。おかげさまで他にはない、たくさんの種類のものを作れるようになりました。そこで培われた技術が受け継がれて、今もいろいろな要望に応えられることにつながっています。在庫管理は大変ですが(笑)、それも大切なことですし、うちの工場ならではと思います」
れんがを数えるとき、昔から職人さんは「丁」というそうだ。この1丁にどれだけの技術と伝統が詰まっているのか。そう考えると、れんがの重みがぐっと一段増す気がした。

米澤煉瓦の定番製品の一部。中央が「普通れんが」の赤色、左が還元色、右は「DIYブリック」という独自考案品で、表面の凸凹を組み合わせて手軽に積むことができる。家庭用ピザ窯キットの販売も考案中

れんが作りに使う木製の型枠。こうした昔ながら道具が残っていることも、多様な要望に応えられる理由の一つ
米澤煉瓦が本州で開かれる建材の展示会などに行くと、よく商談相手から「さすがに詰まってますね」といわれるそうだ。"詰まっている”とは、密度が高く重厚感があるという意味だ。北海道など寒冷地では、れんがが水分を多く吸収すると、凍ったり溶けたりを繰り返してれんが自体が割れてしまうことが多い。
「僕らはこの凍害を防ぐため、昔から吸水率の低い、よく焼き締めたれんがを作ってきました。江別れんがの原料となる野幌丘陵の粘土は、耐火性が高く、高温・長時間の焼成にもち応える良質な粘土で、これが豊富にあったからこそ、寒い土地でもひび割れない、寒冷地仕様のれんがを作ることができました。以前、北海道に海外産のれんがが輸入されたことがありましたが、デザインは抜群に良かったものの、吸水率が高かったせいでボロボロ割れてしまい使い物になりませんでした」と秀則さん。なるほど、れんがも地産地消が一番なのだ。
ここで簡単に、江別れんがの歴史と背景について説明したい。
江別でれんが産業が発展した理由は、大きく4つあげられる。
はじめて生産されたのは、1891(明治24)年、幌向村江別太(現・江別市東光町覚良寺境内)で創業した「江別太煉化石工場」。明治期には6工場が設立され、旭川の陸軍第七師団建設、鉄道工事の拡張、札幌のビール工場、五番館など、各地で利用されて好況が続いた。
本州では1923(大正12)年の関東大震災によって、れんが建築が軒並み倒壊したことから需要が減少したが、北海道では多少の波はあったものの、工場数、製造数とも順調に推移する。戦後復興期でコンクリートなどが手に入りにくかった時代は、建設素材として年間2000万個ほどのれんがが江別で生産・出荷されていた。
しかし、その後は鉄筋コンクリートなどの普及で急激に減少し、各地の工場が閉鎖されていく。以降、江別のなかでも米澤煉瓦のある野幌が生産の中心地として残った。さらに昭和中期以降は、全国的に木造住宅や軽量鉄骨造の普及により需要が減少、現在は全国でれんがを製造する会社はわずか10社程度という。
そうしたなか、江別に伝わるれんが製造の技術、今も残る多くのれんがの建物、それらを活かしたまちづくりが評価され、2004(平成16)年に「江別のれんが」が北海道遺産に選定された。また、2024(令和6)年には江別市が日本遺産「炭鉄港」の地域に加わり、米澤煉瓦の工場も構成文化財の一つになっている。

応接室に飾られた「北海道遺産」(右)と「日本遺産」の認定証
(「炭鉄港」ポータルサイト)

米澤煉瓦のれんがは特別色を除き、100%江別産の粘土を使用している。地元農家と契約して水田や畑の下層部を掘って粘土を採取し、その後は客土をしたり、水はけを良くする土管を設置したりして田畑に戻す

原料の粘土と山砂をブレンドする。製造品によってブレンド比を変えて調合

混ぜ合わせた原料の空気を抜き、型枠から押し出し、1つずつピアノ線でカットして成型する機械

成型後は20日から30日かけて水分を飛ばす。乾燥はれんが製造で一番時間のかかる工程

乾燥後、台車の上に積む作業では熱がむらなく当たるよう細心の注意が必要

長さ83mのトンネルキルン(窯炉)に入れ、2日半から3日かけて焼き上げる。焼成温度は1000度以上。一旦火が入ると24時間3交代体制で、窯内の空気量や燃料の量などを調節し、目指す焼き色に仕上げていく

できたてのれんがタイル。まだ熱いので自然冷却後に紐をかけて出荷する。これは道内の小学校で使われる予定
米澤煉瓦の現社長、米澤照二さんが話してくれた。
「日本のれんが産業の歴史はスタートから200年も経っていませんが、海外に引けを取らない、むしろ優れたれんがを作ってきました。ただ、世界から見たらまだまだ小僧で、れんがの表情一つとっても、イギリスやオランダなどヨーロッパの建物には味があり、そのれんがが小さなハンドメイドの工場で作られていたりします。日本もようやく、そうした『れんがの文化』が生まれるところに来たのかなと思います」

秀則さんの父で米澤煉瓦の三代目社長、米澤照二さん(撮影:伊田行孝)
さらに秀則さんはこう続ける。
「今もたくさんの人から江別が『れんがのまち』と認識されるのはうれしいことですが、かつて基幹産業だった時代とは、ずいぶん違ってきています。だからこそ、今の時代の『れんがのまち』をどう提案していくかがすごく大事で、これまでの歴史をふまえて、現在ここに住む多くの人の知恵を借りながら、きちんと提案し、形にしていきたいと思います。それを先頭切ってやるのは、やっぱり僕ら『れんが屋さん』でなくちゃと思って、いろいろ活動しているところです」
活動の一つは、まずは江別のことを知る勉強。秀則さんは昨年から江別青年会議所に所属し、同年代の25名ほどの仲間と勉強会を行っている。そこでは江別を良くするために、どうやってまちを盛り上げていくか、様々な意見が出るという。
「僕はれんがですが、例えばスポーツや子育ての視点、観光や農業の視点など、本当にいろいろな話題が出てきます。そのどれもが江別の良さにつながっていくし、れんがもその一要素で、れんがをきっかけに地域の歴史に興味をもったり、子どもたちが自分の住む地域を好きになったりするといいですよね」
2025年8月30日、江別青年会議所主催で「まるっとえべつ探検隊」というイベントが開催される。会場の一つは、米澤煉瓦のシンボルとなっている煙突の足元にある倉庫だ。モルタルを使ってれんがを積む体験やミニチュアれんが工作のほか、バター作りや土器作り、地元農産物・特産品の販売、縄文太鼓の演奏など、江別のまちを知るたくさんの視点を文字通り「まるっと」集めて体験できる。

「まるっと えべつ探検隊」のチラシ
(江別青年会議所のページリンクはこちら)
今後はイベントの成果も踏まえながら、倉庫のさらなる利活用を考えているという。「ここでカフェやビアガーデンを開くのも面白いし、コンサートができるイベントスペースもいいかもしれない。いろいろな人が気軽に交流できて、れんがのことを知ってもらえる、オープンな場所になればと思っています」と秀則さん。
明治から続く江別れんがの歴史は、自在に形を変えながら、新しいステージへと移り始めている。

米澤煉瓦のシンボル的な存在の煙突は、1939(昭和11)年に4万個のれんがを用いて建設したもの。石炭焚きの時代から重油となった今も大切に使われている

米澤煉瓦株式会社 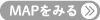
北海道江別市元野幌227番地
TEL:011-382-2801
FAX:011-382-2802
営業時間/8:00~17:00
※土曜・祝日は個別にお問い合わせください。
WEBサイト