

一般的な家の神棚とは明らかに異なる大きさと、並べられた大量の御札(おふだ)に圧倒される。よく見ると、さまざまな神社の御神札(ごしんさつ)と寺院の御札が、かなり古いものから近年のものまで重なり合っている。だが、古い御札はどんど焼きで焚き上げるなどして通常取っておくことはないだろう。そう考えると、このように残されているのは少し不思議だ。
奥にある木製の御札を包んだ紙には「奥寺徳太郎」の名が見える。奥寺家は、ニシン定置網の漁場を持つ「親方」と呼ばれる漁場経営者だった。

包みに「余市町字山碓町 奥寺徳太郎様」と書かれた木の御札
北海道(蝦夷地)の日本海側では、18世紀後半からニシン漁が本格化する。奥寺家は現在の道南・上ノ国町を拠点に、松前藩の漁業経営地であるヨイチ場所(現在の余市町周辺)で出稼ぎ漁を行ってきた。明治維新後は、1870(明治3)年に一家で余市に移住し、ニシン漁場の経営者として名を成す。余市で親方となった有力漁業者のうち、江戸時代から来住した者は上ノ国出身者が多くを占めていた。明治初期には海岸沿いに85戸が並び、とくに奥寺家が居住した山碓(やまうす。現在の港町付近)はニシン漁場の中心だった。
この神棚は、ニシン粕などニシン加工品の輸送に使われた弁才船(べんざいせん・べざいせん)に乗せられていたと伝わる。余市町教育委員会の浅野敏昭さんが、現在も町内で水産加工業を営む奥寺家の調査を行った際、奥寺家に嫁入りした人からそう聞き取った。「おそらく船の帆柱近くに祀られていたと思いますが、通常より大型なのでかなり大きな船だったと想像します」と浅野さん。家の2階の踊り場に、枠にすっぽり嵌まった状態で海を向いて置かれていたものを、2000年ごろに御札ごと譲り受け、史料として収蔵した。
展示では保護のため枠にアクリル板が嵌め込まれているが、特別に外してもらう。その瞬間、木の香りがふわりと漂ってきた。いつ作られたのかは不明だが、つい最近ではないかと思ってしまうほどだ。
御札は明治40年代〜昭和20年代を中心に約90年分、144札以上が収められている。なかでも多いのが現在の山形県鶴岡市にあった湯殿山曼陀羅寺で「海上安全 豊漁満足」が祈願されている。出羽三山の一つ湯殿山は、古くから漁民の大漁祈願の対象だった。湯殿山では定置網ごとの大漁占いを行っていたと思われる。前方の目立つところに置かれた龍澤山善寳寺(ぜんぽうじ)も海の守護神・龍神を祀る鶴岡の寺院で、同じく安全と豊漁を祈願していた。

「湯殿山」とある御札が多く見られる。道内では函館八幡宮、函館水天宮、地元の余市神社。寺院と神社のものが混在して収められている
鶴岡は、いわゆる北前船(日本海回りの商用弁才船)の寄港地のひとつだった。船で関西へ運ばれるニシン粕は綿花栽培などの肥料として最大の売れ筋商品であり、ばく大な富をもたらした。浅野さんは「鶴岡には、親方らが働き手のスカウトと、漁業にご利益のある寺や神社から御札をいただくために訪れていたようです」と言う。
余市では、おもに東北地方からの季節労働者がニシン漁や加工に従事していた。奥寺家は10カ所以上の定置網に関係し、漁業者だけで150人ほどが働いていたという。余市の漁場経営者の平均的な定置網は2、3カ所なので、いかに大規模だったのかがわかる。
善寳寺の御札は木箱に入れて漁船に供えるのとともに、定置網にも同じものを海中に沈め、漁船の御札は漁期が終わると神棚へ移された。また、初水揚げの「初鰊」は真っ先に神棚に供え、今後の豊漁を祈った。
このようにニシン漁と信仰は深く結びつき、神棚はニシンをめぐる生活の中心にあった。御札を代々残してきたのも、その現れだろうか。
「ただ、奥寺の親戚の家の神棚では御札をためていなかったんです。家ごとの違いは何なのか、奥寺家以外ではどうなのかなど、よくわかっていません」と浅野さん。また、奥寺家には神棚が2つあったと聞き取っているそうで、これからの調査が待たれる。


大川遺跡から出土した、しずく型のガラス玉(12世紀ごろ)
余市町は、ニシン漁の文化だけでなく北海道の考古学にとっても重要な地である。
町の中心部を流れる余市川河口近くの大川遺跡は、縄文時代晩期(約3000年前)から近世・近代までの遺構や遺物が出土しており、なかでも墓が多く見つかっている。
学芸員の髙橋美鈴さんが注目するのは、副葬品のガラス玉だ。大川遺跡からは、続縄文文化期(約2000年前)〜アイヌ文化期(中世・近世)と幅広い時代のガラス玉が出土している。髙橋さんによると、一つの遺跡でそれぞれの時代のものがまんべんなく出るのは珍しいという。「葬送儀礼には当時の社会が現れます。そのため、時代ごとに社会がどう変わっていったのかを知るのに有効な遺跡と言えます」。
ガラス玉は、交易品として外からもたらされるものだった。余市川河口は、各時代を通じて石狩低地帯への日本海側の玄関口であり、交易品の流通拠点だったと考えられている。髙橋さんは「ガラス玉という小さなものから、どのような経路で物を入手していたのか、どことつながりを持っていたのかといった当時の社会が見えてくる」と言う。
とくに、しずく型のガラス玉は、中世アイヌ文化期の遺跡から見つかっている。このころになると、本州ではガラス玉は装身具ではなく仏具にしか使われなくなっていた。
北海道では擦文文化期〜アイヌ文化期が始まったころで、同じようなしずく型のガラス玉は厚真町の上幌内2遺跡(約1000年前)などでも出土している。厚真川も内陸への太平洋側の玄関口だったことから、しずく型のガラス玉は大陸および本州との特別なつながりを表していると言えそうだ。

下から光を当ててみると、青緑の美しい色が現れる。髙橋さんによると、「本州でも類例がほとんどなく、交易用のガラス玉だったのかもしれない」とのこと
北海道ではガラス製作は行われず、全て交易品となる。アイヌの人々にとって、ガラス玉は特別なものだった。アイヌ文化期にはおもにサハリンを経由した大陸との交易で手に入れていたが、のちに直接交易することが禁止され、松前藩との交易で得るものとなる。余市などのニシン漁場では、アイヌの人々は労働の対価としてガラス玉を手に入れるようになっていった。
とくに鮮やかな青色の「青玉」が好まれ、時代とともに大玉になる。女性はそれを首飾り「タマサイ」などに仕立てて宝とし、母から娘へ伝えていった。松前藩のもとでの過酷な労働と引き換えだった点は見過ごせないが、ニシン漁を通じて手に入れたガラス玉を自分たちの文化に取り込んでいく過程は、地域の歴史を考える上でも興味深い。

大川遺跡の墓から出土した、17世紀ごろのガラス玉の首飾り。トンボ玉と呼ばれる模様が付いたものは日本製
ヨイチのアイヌ関係史料では、シャチをかたどった祭具も必見だ。日本海側の一部で用いられていたとされ、現存しているのはここ余市のみ。海を通じて外の世界とつながっていた人々の痕跡を、確かに感じられるだろう。

海で最上位のカムイ・シャチをかたどり、家の祭壇に掲げていた「カムイギリ」。これは戦後に再現されたもので、フロア中央には17世紀ごろと思われる古いカムイギリが展示されている。下にニシンやサケなどの魚がぶら下がっているのがかわいらしい


余市水産博物館 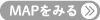
北海道余市郡余市町入舟町21
電話:0135-22-6187
開館時間:9:00〜16:30(最終入館)
休館日:月曜(祝日の場合は開館)、祝日の翌日
※冬期間(12月中旬〜4月上旬)は閉館。令和7年度は4/12〜12/14まで開館
※ゴールデンウイーク期間 は、5月6日(火)まで休まず開館(7日は振替休館)
入館料:大人300円、小中高生100円