
中標津町開陽台から見渡す、道東らしい大牧場の風景。この大地の前史に興味は尽きない

中標津町開陽台から見渡す、道東らしい大牧場の風景。この大地の前史に興味は尽きない
イギリスの歴史家アーノルド・J・トインビー(1889-1975)は、夫人とともに1956(昭和31)年の2月から驚くべき長旅をした。ニューヨークのロックフェラー財団の助成を受けながら、南米から西へ向い南太平洋、東南アジア、日本、中央アジア、中近東と、1年半で地球を一周するのに近い距離を移動したのだ。報告としてまとめられた長大な紀行が、『東から西へ』だ。
20世紀最大の不幸であり愚行であった第二次世界大戦が終わってまだ10年と少し。2月下旬にジャマイカからはじまった旅程は、7月にはオーストラリア、9月にはインドネシアやシンガポールに北上して、ベトナムや香港を経て日本をめざす。横浜に上陸したのは10月頭。日本では六本木(東京)の国際文化会館をベースに、京都や奈良、神戸、そして福岡や長崎にまで足を伸ばし、そこから一転北上した。青函連絡船で青森から函館に上陸したのは11月中旬。一行は鉄路で函館、小樽、札幌をめぐり、そこから車で道央を長沼や遠浅(安平町)、そして白老から登別に入る。登別からは鉄路で函館に戻り、再び連絡船で津軽の地へ。そこから越後をまわって東京。東京から空路で香港、バンコク(タイ)に向かった。
『東から西へ』でトインビーは、3日と少しの北海道滞在を綴った節をこうはじめる。
ひとつの群島中の最北端の島は、いつもなにか特別な価値を持っているように見える。スマトラはインドネシアの希望の島であり、北海道は日本の期待の島である。この北海道に、今日すでに未来の日本を見ることができるのだ。
「ひとつの群島中の最北端の島は、いつもなにか特別な価値を持っているように見える」という一節はいまでも道産子を十分に気持ち良くしてくれるが、トインビーは札幌郊外の玉ネギ農家と長沼方面の米農家、そして安平の酪農家などを訪ね、聞き取りをしている。そして明治初頭、開拓使のリーダーだったホーレス・ケプロンばりに、米は決して北海道向きの作物ではない、と強調する。一方で西洋に学ぶ酪農家を絶賛。米作農家は日本式の家を建てて、神棚と仏壇を設け、先祖の肖像写真をずらりと並べていたが、酪農経営者はアメリカ型の2階建ての家を建て、イスとテーブルで食事をしていたことを高く評価した。
あの革命的な酪農家の孫たちは、かれらと同じ世代のウィスコンシンやミネソタの農家の子弟と同じように近代的になるに違いない。
トインビーには、敗戦によって日本の戦前の思想的世界が崩壊して、それはなお空白のままになっていると見えた。日本は、ほかのアジア諸国に先駆けて西欧の近代的文明に向かって計画的に門戸を開いた国であるが、伝統の威力が強く、過去と未来がつねに緊張関係にある。
ところが、北海道は日本列島の中で、1300年間にわたる西欧化以前の日本文明によって築き上げられた伝統が、本来のまざり気のない形態で存在したことのないただ一つの島である。
文化人類学者梅棹忠夫は「北海道独立論」(1960年)で、このトインビーの考えを自身の論考の入り口にしている。曰く、トインビーは北海道において日本の未来像を見た。しかし実際には、内地の姿が北海道を満たしていった。北海道の文明が安定して成熟するほど、内地との同質化は進み北海道は内地に似てくる。北海道にあるものは、伝統的な日本文明の新しい環境に対する適応であり特殊化である。それは日本文明の変種であり、亜種であった、と。
開拓がはじまってすでに一世紀。ここにはなにかあたらしいものがありえたはずである。しかし、現実にはあたらしい文化はうまれてこなかった。理想は実現しなかったのである。
北海道論をめぐるトインビーと梅棹のこうした論考は今でもしばしば参照される基本的なリソースでありつづけているが、そこには太古からつらなる先住の人々の長く複雑な歴史が含まれていないし(考古学者河野広道の北海道独立論も同様だった)、列島の情報化と均質化が猛烈に進んだ現代では、「中央」と「辺境」の関わりをストレートに論点とするのも難しい。しかしこのサイドストーリーの初回では、「産業遺産や産業考古学は、『かつてありえた北海道』の時代の地図を作り直すことができる」、と書いた。回り道をしながら、そこへ向かって少し進んでみよう。
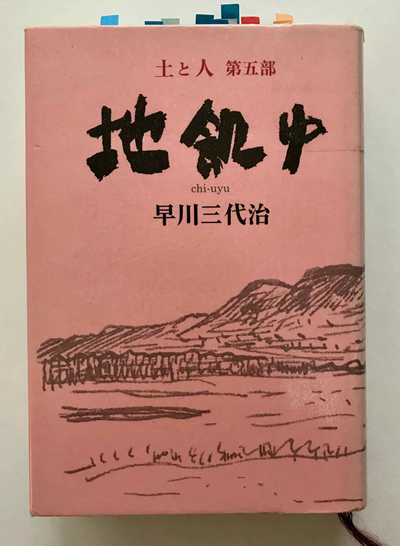
早川三代治「土と人」第五部『地飢ゆ』。関係者の尽力により、「北方文芸」に15回連載された40数年のち、2012年に単行本化された
イギリスの映画監督ケン・ローチの作品は、近年の「わたしは、ダニエル・ブレイク」や「家族を想うとき」でいっそう研ぎ澄まされているように、社会の弱者の現実を細部までとてもリアルに描き出す。そこには希望はおろか心地よい感傷のかけらもない。人はなぜ、そんなやり切れない世界に惹かれてしまうのだろうか。演劇論ではそれをカタルシス(作品によって呼び覚まされる精神や感情の浄化)と定義するのだろうが、僕たちはなぜ、救いようのない物語をまた観たい、あるいは観なければならない、と思うのだろう。
すぐれた悲劇の核心は、単なる作者の自己表現ではなく、受けとめる側の自己や創造性をどのように刺激したり開放していくか、という局面にあるのだろう。20世紀前半の米国東部で、貧しい入植者の日常を描きつづけたアンドリュー・ワイエスの絵画が観る者を射るのも、アメリカンドリームと現実とのはざまで寡黙に生き抜くしかなかった市井の人々がもたらす、思いがけない気づきや共感かもしれない。
北海道開拓をテーマにした文学や映画はこれまで無数に作られてきた。例えば「原野と戦い社会に翻弄される人生」というオーソドックスな主題では、吉田十四雄(としお)の『人間の大地』がある。全8巻からなるこのノンフィクションを思わせる長編小説では、原始のままの十勝の大地を人間の土地にするために、明治末に岐阜から中札内に渡って数々の壮絶な苦悩と格闘する男が主人公だ。大正から昭和へ。男は300万坪の地主にまでなったが、戦後の農地改革で無惨にもそのほとんどを失ってしまう。
そしてどこまでも救いようのない開拓の辛苦を繰り返し書き続けた経済学者・作家に、小樽に生まれた早川三代治(みよじ)(1895-1962)がいる。
早川の実家は、明治初頭に越後から小樽に渡った祖父が起こした商家で、醤油や亜麻油の製造や米穀取引、精米などで財をなし、不動産にも事業を拡大した。1921(大正10)年に北海道帝国大学を卒業するとドイツのボンやベルリンで最先端の経済学を学び、帰国すると北大で教鞭をとりながら国際的な経済誌にも論文を発表する。戦後は小樽商科大学教授を務めた。
早川三代治は、入学した東北帝国大学農科大学(現・北海道大学)で英語の担当教授だった有島武郎と出会い、深く傾倒する。境遇やスケールはちがうものの、豊かに「持てる者」という共通の出自があった。2016年の春に小樽文学館と小樽商科大学が連携して開いた早川の特別展は、経済学から文学、そして美術にまたがる早川の大きな全体像が幅広くわかる刺激的な企画だった。
早川三代治が生涯をかけて取り組み、最終巻に手をつける前に生を終えてしまった大作に、「土と人」という六部作がある。いま手に入りやすいのは第二部「処女地」(「北海道文学全集第9巻」立風書房)と第五部「地飢ゆ」(中央公論事業出版)のふたつだが、1929(昭和4)年の春からはじまる第一部から全体をとおして、舞台は北海道東部、標茶町北部に位置する虹別原野に設定されている。寒冷で火山灰質の劣地であるために、明治大正期の開拓熱からは縁遠かった土地だ。早川は最先端の計量経済学者の才知と文学者のまなざしで、虹別原野を見すえつづけたのだった。
大正末期、移住熱が一段落した北海道はさらなる入植者を求めていた。第一次世界大戦後の経済不況もある。内務省では開墾出願者の中から成功の見込みのある者を選び、「許可移民」として補助金を支給した。用意されたのは、一戸あたり10町歩(約3万坪)もの原野だ。自作農になる夢を抱いて、関東大震災(1923年)の罹災者をはじめ、全国からさまざまな人々がこの地にやって来る。なにしろ開墾に成功すれば、凶作と年貢に苦しめられながら農場を渡っていく小作ではなく、内地ではかなわなかった自作農家になることができるのだ。
虹別には移民世話所が設けられ、道庁職員が駐在した。当初の4年間(1929〜1933)で340戸以上が入ったが、1933(昭和7)年は北海道史に残る道東大冷害の年で、すでにその時点で約130戸がこの地をあきらめた。
「土と人」の第二部「処女地」では、入植したものの凶作に打ちのめされた一家が夜逃げをして、自らが見つけた土地に不正に入植する。しかし、丹頂鶴が美しく舞うその地はさらにひどい泥炭地で、子どもや母が亡くなり、妻の狂乱も重なって結局土地を捨てる。残された子どもを手放した主人公の男は、鉄道自殺を図るも死にきれず右足を失い、結局雪解けのアシ原で腐乱死体となって発見された。徹頭徹尾、まったく救いのない結末だ。
第五部「地飢ゆ」では、太平洋戦争で働き手を兵隊に取られていく虹別が舞台となる。冒頭で展開されるのは、1943(昭和18)年9月に札幌の中島公園で行われた、アッツ島(アリューシャン列島)の戦いで玉砕した2千数百の兵士たちの慰霊祭だ。戦中戦後の食糧難で農家の生産物は高値を呼び、それを良いことに、虹別でも人々は土づくりよりも目先の収奪農業に明け暮れた。厳しい自然と、商人や開拓民が抱える人間の業(ごう)によって、見るまに大地が飢えて(痩せて)いく。早川は、死によって、あるいは離農で開拓一世がさまざまに土地を去って行くさまをリアルに描き出した。

大盛況だった「簡易軌道シンポジウムin鶴居村」(2019年11月17日)
札幌の平岸に生まれリンゴ園も営んだ作家澤田誠一はあるエッセイで、「北海道で農民は定住するが、先祖代々はなく、隣近所は永久ではない」、と書いている(「故郷の喪失・故郷の創出」)。人間の苦悩や哀切に、上澄みの好奇心や同情、あるいは憐れみとはちがう次元で共感していく心情は、産業遺産をめぐる言説とどのように関わってくるだろうか。
1995年に刊行された堀淳一(物理学者・随筆家)のガイド本『北海道産業遺産の旅』は、「廃墟の憂愁はあらがいがたく人を魅する」、とはじまる。堀は、いにしえから都市の営みの中心にあった城砦(じょうさい)や大寺院は人々を誘い、「哀切の情感と、歴史とはなにか? 人生とは? 宗教とは?」という思いに人を引きずり込むと言い、ならば、近代に発達した工場や社会インフラも同じように見られないか、と問う。そして産業遺産は人々に、「国家とは? 産業とは? 近代文明とは?」という思いをうながし、太古の廃墟と比べても、「滅びの哀愁にも、人にもの想わせる力にも、何等逕庭(※けいてい・隔たり)はないのである」、と訴えている。にもかかわらず人はなぜ産業遺産はかえりみないのか。そのもどかしさが著者をしてこの本を書かせた。
堀の著作から25年がたち、産業遺産をめぐる言説は少し文脈を変えながら、廃墟マニアの旅人ではなく、あくまで地域を主語にして動くようになっている。旅する人ではなく、旅される人が主語になることが重要だ。
昨年(2019年)11月に道東の鶴居村で開かれた「簡易軌道シンポジウム」に参加して、その盛況ぶりに驚いた。これは2018年11月に「簡易軌道」が北海道遺産に選定されたことを記念して開かれたもので、3つの講演と各地からの報告をまじえたこれからのビジョンが話し合われた。
簡易軌道(開拓時代は殖民軌道と呼ばれた)とは、北海道の内陸開拓のための交通インフラとして敷かれた、軌間(レール幅)が狭い鉄路だ(在来線の1,067mmに対して762mm)。国鉄の線路と結ぶことはできないが、建設も運営もぐんと低コストで済む。当初の動力は、馬だった。
『釧路・根室の簡易鉄道』(釧路市立博物館)によれば、火山灰地や泥炭地を踏み固めただけで春先には泥沼のようになってしまう当時の道路に比べて、レール・枕木・道床で構成される軌道は格段に有効で、大正末以降、入植地へ細い2本のレールが延びていくことになる。
簡易軌道は1960年代で姿を消していくが、道東を中心に近年、このレールをめぐる地域の再発見と再認識が進んでいる。忘れられたレールが結んだ人やモノ、そして産業の動きをたどり直すことで地域史に新たな光が当たり、その光が触媒となって住民たちの郷土意識にも変化が生まれる。原野に毛細血管のように敷かれた簡易軌道は、それだけ人々の営みの内側に深く関わっていたのだ。そして全国の鉄道ファンを中心に、裾野の広い観光の有力なコンテンツとして、地域経済にも魅力的な糧をもたらそうとしている。
地域自身による簡易軌道の再発見と再認識は、廃墟マニアの心情を少しずつずらしながら、「あらがいがたく人を魅する廃墟の憂愁」(堀淳一)に新たな価値を加えることができる。
綿密な取材とデータ分析の上に早川三代治が描き続けた虹別原野にも、2本の簡易軌道があった。虹別と弟子屈(てしかが)を結ぶ弟子屈線(22km)と、虹別と西春別を結ぶ虹別線(9.6km)だ。正確な産業経済史に根ざす早川文学の世界は、いまならさらに新たな読み方ができるのかもしれない。地域の営みを、悲劇や憂愁の内側から未来に向けて読み解き、創造的に語り開いていくことができないだろうか。
道東の簡易軌道については次回にもふれよう。

道東の簡易軌道を知るためのバイブル。『釧路・根室の簡易軌道』(釧路市立博物館)