
産業革命の生地と呼ばれる、イングランド中西部シュロップシャー州のアイアンブリッジ。セヴァーン川に架けられた世界初の鋳鉄製のアーチ橋。1781年開通(著作者:Roantrum、2005年、via ウィキメディア・コモンズ)

産業革命の生地と呼ばれる、イングランド中西部シュロップシャー州のアイアンブリッジ。セヴァーン川に架けられた世界初の鋳鉄製のアーチ橋。1781年開通(著作者:Roantrum、2005年、via ウィキメディア・コモンズ)
前回の冒頭で歴史家アーノルド・J・トインビーの長い旅(1956年)にふれたが、さかのれば日本にも明治のはじめ(1871〜73)、歴史に残る大きな旅をした人々がいた。右大臣の岩倉具視をリーダー(特命全権大使)にして政府の高官や実力者たち50名ほどが、1年10カ月もの期間を費やして欧米12カ国をまわった、いわゆる岩倉使節団だ(派遣された留学生を含めると百名を超す)。通信や交通の手段も限られ、国の形もまだ定まらないこの時期にこれだけの規模の海外視察が行われたことには驚くしかない。
岩倉のほか主要メンバーには、旧長州藩士の木戸孝允と伊藤博文、薩摩藩士だった大久保利通、旧佐賀藩士の山口尚芳がいて、開拓使の実務を立ち上げた公家の東久世通禧(ひがしくぜみちとみ)といった名前もあがる。平均年齢は32歳。最年長は岩倉の47歳で、伊藤博文は31歳。最年少は18歳の権少判事(下級の判事)、長野文炳(ふみあきら)だった。
彼らの狙いは、徳川幕府を滅ぼしてリセットした新生日本を欧米と同格の近代国家へ立ち上げていくために、西洋社会の成り立ちを体験的に調査して学ぶことにあった。各国首脳や王族との面会も重要な目的で、幕末に強いられた不平等条約群の改正のための予備交渉にも取り組んだ。同行したのちの歴史学者久米邦武がまとめた報告が、大部の『特命全権大使 米欧回覧実記』だ。
一行はアメリカの蒸気船会社の定期旅客郵便船に乗り込み、1871(明治4)年12月下旬(以下新暦)に横浜を出港。1月上旬にサンフランシスコに上陸して、鉄路で大陸を横断しながら、新興国アメリカの開拓のようすを見て、2月末に首都である東海岸のワシントンD.Cにたどり着いた。そこでようやく条約改正のための会談が何度か持たれ、東部エリアも精力的に視察した。アメリカ視察に費やした期間は8カ月にも及ぶ。イギリスから独立(1776年)して100年にも満たないこの大国が、短期間でどのようにして産業を興し、社会を作り上げていったのか—。彼らは教育やキリスト教の役割の重要さにも目を開かれていった。
ボストンから大西洋を渡ってイギリスをめざしたのは、1872(明治5)年8月上旬。アイルランドのコーブを経てリバプールに上陸。鉄路でロンドンをめざして東進した。ロンドンのユーストン駅に到着したのは、8月17日の深夜近くだった。その後一行は4カ月以上をかけて、リヴァプール、マンチェスター、グラスゴー、エジンバラ、ニューカッスル、シェフィールド、バーミンガムなどを視察。ロンドンでは議会を見学したりヴィクトリア女王にも謁見している。
岩倉らがイギリスでとりわけ貪欲に見て回ったのは、造船場や紡績工場、製鉄場やビール醸造所など、世界の産業革命を牽引してきた国の工業の現場だった。
久米の『特命全権大使 米欧回覧実記』には、例えばスコットランド南西部の工業都市グラスゴーの造船所は、構内に3500人もの職人が働き、同時に12隻の鉄の蒸気船が造られているなどと淡々と記され、素材や工程などにはじまり船の売値のことまでが詳細に聞き取られている。情緒的な記述のほとんどない文章には、目を見張るもののすべてを文字によってできるだけ正確に写し取ろうという意思がみなぎっているようだ。
歴史学者田中彰は『明治維新と西洋文明—岩倉使節団は何を見たか』で、実記のイギリスの部は、「この国の産業革命の歴史と現状報告といえる。それは日本でのもっとも早い産業革命レポートではなかったか」、と書いている。

岩倉使節団の主要メンバー。左から木戸孝允、山口尚芳、岩倉具視、伊藤博文、大久保利通。ロンドン滞在中に撮影(1872年)(Licensed under パブリック・ドメイン via ウィキメディア・コモンズ)
さて最初にロンドンに入った一行が降り立ったユーストン駅こそ、20世紀後半からイギリスで発展した産業考古学にとって、重要な意味を持つ場所となるのだった。産業の革命をリードした国であるイギリスでの、産業考古学の大きなアウトラインをさらっておこう。
ユーストン駅は、蒸気機関車の父であるジョージ・スチーブンソンの息子、ロバート・スティーブンソンらが建設したロンドン・アンド・バーミンガム鉄道のターミナル駅として、1837年に開業した。先進の設計と技術が完成させた駅としても世界の鉄道史上きわめて重要な駅だったが、蒸気機関車の時代が終わりを迎えた1960年代になると機能的に時代遅れになり、建て替えが決まる。
イギリスの歴史ライター、ティム・クーパーの『How to Read Industrial Britain』などによれば、しかしこのときに起こった議論が産業考古学という新しい世界を広げることになった。このころ北米の東海岸などではすでに歴史建築を保存する動きがあり、歴史ある建物や景観を都市計画の中に活かして行く取り組みがはじまっていた。
1970年代に入ると、イングランド中西部シュロップシャー州にある古い鉄橋の保存が決まり、橋を中心にした歴史遺構の再生事業が注目を集める。1781年に架けられた、世界最初期の鋳鉄(ちゅうてつ)製のこのアーチ橋は、その名もアイアンブリッジ。古くから鉄鋼業で栄えた地域のシンボル的な存在だったが、やがて一帯は自ら「産業革命の生地」を名のるようになる。同時期に、紡績の機械化に成功したリチャード・アークライトの工場(イングランドの中央部クロムフォード)の復元保存も話題を集めた。
ティム・クーパーの前掲書によれば、しかしこうした動向がより広く注目されるようになるには外部からのまなざしが必要で、アイアンブリッジが国内外からのツーリストを集めるようになったきっかけは、なんと日本から押し寄せはじめた観光ツアーだったという。
自分たちにとってはさほど意味のないものが、他者のまなざしによって新たな意味を帯びていく—。現代の観光では、観光地のコンテンツがツーリストによって一方的に消費されるのではなく、旅する人と旅される人との交わりによって新しい価値が生まれることを期待されているが、産業遺産はまさにそうしたオルタナティブ・ツーリズムの源流のひとつに位置づけられるだろう。
イギリスの人々は自分たちのふるさとが産業革命の生地であることを改めて意識して、その遺産とそれらが配置された景観がまだある程度残っていることに気がついた。世界中でこんな場所はほかにないのではないか。その気づきが地域の経済文化に内発的な力をもたらし、観光の切り口から公共政策にまで影響を及ぼしていく。
イギリスの歴史家や保存の運動家たちは産業革命の遺構群を、さながら古代の地中海文明のように、新たな文明の勃興を体現した記号であり具体的な遺跡として見出した。さらに現代は、それらをまだ生きたものとして活用することができる。彼らは、現代社会はそれを保存も、活用も、破壊もできる特別なポジションにあるのだ、と訴えた。進路を決めるのは、あくまで地域が主語になった取り組みだ。
そうして前述したアイアンブリッジや、イングランド北部のビーミッシュなどがオープンエアの野外博物館として整備されていった。往時の姿を空間的な景観としても、成り立ちの歴史文脈ごと残して活かそうという試みだ。つまり産業遺産は、単に歴史をふりかえる手段ではなく、まちを再生したり活気づけていくための手法や触媒として位置づけられていったのだ。
1980年代に入るとこうした事業は、リバプールの港と倉庫群の複合体であるアルバート・ドックが、物販や飲食の施設に、現代美術や歴史のミュージアムも加えて複合的に再生されたように、その規模とコンセプトを拡張していく。それはまた、工業化社会からポスト工業化社会の変容をわかりやすく刻印する再開発ともなった。
21世紀に向かってイギリスでは(日本でも同様だが)、歴史遺産の再生は、工場跡地を大規模なアパート群にしていくような、都市の住環境のリノベーションの分野にも広がっていく。
ティム・クーパーは、イギリスの産業遺産は単に過去のモニュメント群であるにとどまらず、近代の産業社会の多様なレイヤーが織り込まれた複雑なタペストリーだと訴える。それらは文明の基盤として現代人に受け継がれながら、次の世代へと、人間の新たな営みを呼び起こし触発していくものなのだ。
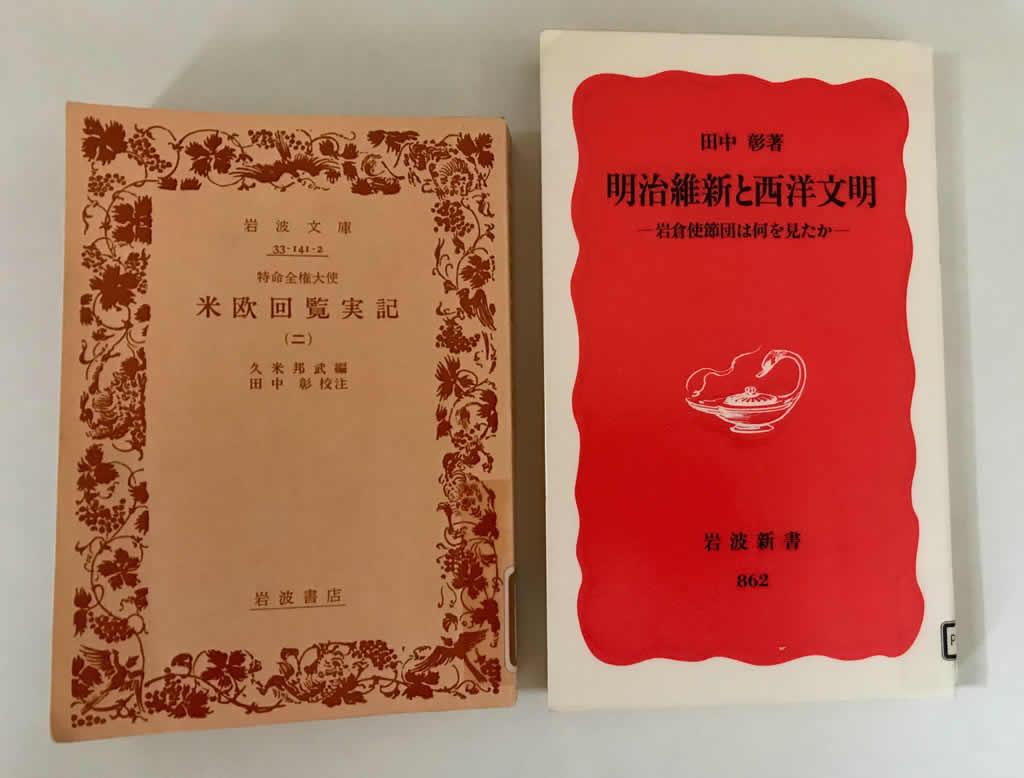
岩倉使節団のイギリスの旅が綴られた『米欧回覧実記(二)』。田中彰『明治維新と西洋文明』
北海道は日本の中で最初期に産業革命の波が寄せた土地であり、その理念と実践によって、蝦夷地は北海道へと深く変容していった。
ペリー艦隊の来航によってまず下田と箱館が開港(1854年)されると、蒸気船の燃料になる石炭が必要になり、幕府(箱館奉行所)は岩内(積丹半島の西の付け根)近郊の茅沼で発見された石炭を掘り出すことにする。採鉱や築港のために20人以上の御雇外国人が岩内に派遣されてインフラの整備が進み、鉄軌道も敷かれた。こうして日本海に面した蝦夷の寒漁村がいっきに先進技術のブームタウンになったのだが、これらの事業や動向は、明治の開拓使にも引き継がれていく。岩倉使節団がイギリスで吸収しようとした近代工業が、北海道開拓にはとりわけ欠かせなかったからだ。北海道の開拓史を石炭・鉄鋼・港湾・鉄道というテーマでくくる「炭鉄港」という日本遺産は、そうした文脈のエッセンスをすくい取ったものだ。
歴史学者田中彰は岩倉使節団を考察した1970年代のエッセイで(北海道新聞1974.11.27「岩倉使節団とアメリカ」下)、「岩倉使節団は、アメリカ文明の何たるかを洞察しつつも、その民衆の生活に根ざしたもっとも肝心なものは、惜しげもなく捨て去った」、と論じている。彼らには、人民こそが国家の主人公であるというアメリカ建国の理念には関心を寄せることなく、天皇を軸にした近代国家の骨組みと輪郭を一刻も早く組み上げていくことがミッションだったからだ。
社会の骨組みと輪郭のあいだを埋めるのは、庶民の複雑な関わりが構成する社会であるはずだが、明治から現代まで、日本ではこの中間領域への意識がつねに薄かった。以前、札幌出身の名クラリネット奏者である村井祐児さんを東京藝術大学に訪ねたことがあった。札幌での思い出や修業時代のことを聞いたのだが、そのとき村井さんは、「日本はさながら内声部のない社会だ」ということを繰り返し語っていた。内声部とは、オーケストラでは第二ヴァイオリンやヴィオラが担う、音楽の豊かなふくらみを内側から作り出す重要なパートだ。
歴史学者與那覇潤(よなはじゅん)もすでに2013年に発表した『史論の復権』の前書きで、いまの日本社会が抱える問題の多くは、「中間的なもの」の衰退ということに尽きる、と述べている。経済で見ればグローバル化によって階層の二極化が進んでいるが、人物や政策などの面においても、世の中の評価は短期間に絶対善から絶対悪に変わってしまう。社会が示す態度として、あまりにも中間がないではないか、と。
この連載の初回でふれた歴史学者大濱徹也(1937-2019)は、『日本人と戦争』の中で、「思えば戦後日本は、歴史を旅することもせず、歴史を断罪してことたれりとする風潮に流されてきた」、と言う。
僕たちにはいま、社会や歴史の、内声部の響きをていねいに味わうことが求められているだろう。大濱は同書の「民衆の原像としての兵士」と題した章で、「地方史研究が負わされた課題の一つは、民衆がどのように生きたかを、生活の場で解析すること」、と書く。これは国家、天皇制、教育といった大きな概念(骨組み)で説けるものではなく、「地域的個性をおびた存在として検討されなければなりません。いわば民衆は、生活が負わされた地域差をふまえた時、はじめて具体像を提示することが可能になります」
歴史は、大きなイデオロギーに拠って断罪するものではなく、小さな足取りで旅するもの。大濱は、戦争という、断罪するしかないと思われるほど重たいテーマに取り組みながら、そう呼びかけた。
地域の歴史を、いまだからできる方法で多様に旅すること—。その道案内でありヴィークルとして、近年の北海道には例えば「簡易軌道」がある。この特集でも登場していただいている石川孝織(釧路市立博物館学芸員)さんたちの挑戦は、わかりやすいアイコンを並べるだけで内声部がおろそかになりがちな北海道の旅や地域研究に、新たな地図を用意してくれている。そこから生まれるのは、ある時代のある土地における小さな出来事のつながりを生活の場から問い質し、意味づけながら描き出そうとする、魅力的な内声部をもつ物語だ。
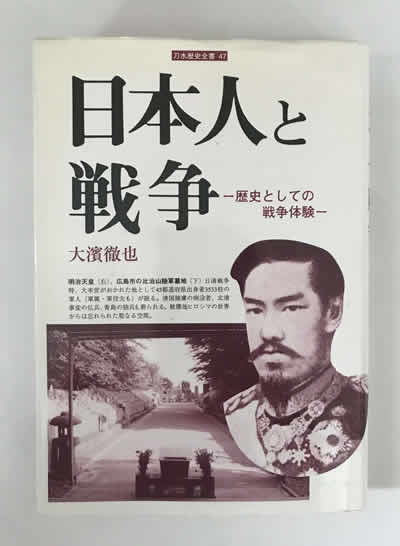
大濱徹也『日本人と戦争』